クラリネット演奏における速いパッセージや連符は楽器の特徴を生かしており、音楽的にも魅力が多い場所です。
一方、速いパッセージや連符が苦手だったり、どうしても特定の速さの先に進めないという悩みも多いです。
速度感のある音楽については、毎日メトロノームをカチコチ鳴らし、そのテンポを上げていけば必ず上がる、というわけでもありません。
その練習過程には観察するべきポイントと過程があり、それを無視するとどうしても「テンポの壁」にぶつかり、演奏をのびのび楽しむことを阻害します。
この記事では、社会人として忙しくしていても、限られた練習時間でテンポアップを能率よく進める方法を解説します。
どうしてテンポアップがうまくいかないのか

まずは、なぜテンポアップがうまくいかないのか、どんな時につまづいてしまうのか考えてみましょう。
あなたの状態に最も当てはまることは次のうちどれでしょうか。
音楽の方向をわかっていない
その連符がどこに向かうのか。あるいは、連符ひとつの中にどういった盛り上がり、ピーク、落ち着きがあるのかを無視すると、テンポアップの限界がやってきます。
例えメトロノーム通りの速さで吹けたとしても、音楽的意味を含まないのっぺらぼうな演奏になります。
こうなると、どれだけ正確に演奏できても、プレイヤーも聴衆も腑に落ちず「吹けてない」という結論に至ります。
やり方をまだ知らないのに速く吹こうとしている
体の使い方、息のバランス、アンブシュアのコントロール、運指のつながりなど、
そのパッセージを吹くための「やり方」をまだ知らないうちは速く吹くことは不可能です。
フレーズの構造パターンをわかってない
その連符やパッセージの構造はなんですか?
- 何調のダイアトニックスケール?アルペッジオ?
- トニック→ドミナント→トニックの流れ?
- リズムパターンは?
- バックに流れているであろう和音は何?
- 結局何調の音楽?
音符を単独で考えているとテンポアップに限界があります。連符や速いパッセージを演奏する時、ただ楽譜にある通りに音をひとつづつ処理するのは本番のステージでは通用しません。間に合いません。
演奏は瞬間だからです。
しかし、パッセージをひとまとまりに、または任意に区分してグループとして認知するとワーキングメモリが節約できます。
例えば、「おはよう」という挨拶が「お」と「は」と「よ」と「う」でなく、「おはよう」のひとまとまりで意味も言葉としての美しさも併せ持つように。
なので、フレーズやパッセージの構造パターンを知ることが有効です。この作業を省くとテンポアップに限界がすぐやってきます。
また、こういった分析に役立つのが、普段取り組んでいるスケールやアルペッジオなどの音階練習です。
楽譜に書かれてあることを素早く理解し、すでに身についている技術を活用して、速いパッセージを効率よく会得します。
*だからと言って、スケールを吹けないと曲を吹いちゃいけないとは、私は考えません。双方をバランス良く組み合わせることで上達は促進されます。
難しいままテンポアップしようとしている
「速いテンポでできるということは、つまり、それが自分にとって簡単なことになっているということだよ」
Herman Braune(オランダ/クラリネット奏者・教育家/元アムステルダム音楽院及びユトレヒト音楽院教授)
私の音楽と人生を救ってくれた、オランダの恩人の言葉です。
つまり、自分にとってまだ難しい状態なのに無理して速く吹こうとしているときはテンポアップにつまづきます。
そして、簡単な状態とはその箇所の演奏が習慣化し、なんの疑問ももたず、スラスラできる状態です。
楽しくって何回も繰り返しちゃうレベルです。
お箸を使ったり自転車に乗る時、いちいち考えたりしないのと同じ状況ですね。
自分の心を無視している
不安、焦り、恐怖を無視したまま練習を続けていませんか?
そしてただ「間違えなかった/間違えた」だけで自己評価をしていませんか?
これでは本番で実力を出し切ることはできません。心を無視した状態が常態化しているからです。
無視して「なかったことにしていたもの」が、ステージの上ではさらに強大な力をもって脳裏を猛スピードで駆け抜けます。
自分がそのパッセージを演奏しているときに、どういったどういったメンタルでありたいのかを、ゆっくり練習の時から技術と共に学んでいく必要があります。
テンポアップの練習手順

では、実際にテンポアップしてフレーズをスラスラ演奏するには、どのような練習手順を経るといいのでしょうか?
本番で練習の成果を発揮するには、次のステップに沿うのがよいでしょう。
テンポアップの練習手順
- パッセージについて知る&分析する
- うまくいくやりかたを探す
- やりかたを自分に教える
- 指定テンポ60%でスラスラ度をあげていく
- テンポアップ期間
- 演奏の質を上げる
- テンポの壁に当たったとき
- メンタルに向き合う
ひとつづつ解説します。
パッセージについて知り、分析し、グルーピングする
人間は得体の知れないものに恐怖を覚えます。すると体が固ったりパニックになります。しかし、一旦それが何であるかわかれば、何も怖くはありません。速いパッセージについても同じことが言えます。
ヒント
パッセージがスケールやアルペッジオだったら何調のどんなパターンか分析します。臨時記号が付いていても冷静に、どの調か判断しましょう。これにより普段の基礎練習を役立てることができます。
スケールやアルペッジ以外のものは、パッセージにどんな特徴があるのかよく観察しましょう。さらに、自分にとって理解しやすい固まりにグルーピングしていきます。
スケールやアルペッジ以外のものは、パッセージにどんな特徴があるのかよく観察しましょう。さらに、自分にとって理解しやすい固まりにグルーピングしていきます。
このグルーピングは拍単位の小さなものです。練習はこの最小単位を理解することが大事です。それらをつなげて1つのパッセージを作っていきます。
うまくいくやりかたを探す
このステップをすっ飛ばすと、やり方を知らないまま練習することになるので、後のテンポアップの途中でくじけます。脳内でも情報が混乱し、パッセージとパニックがセット記憶されます。何もいいことがありません。
連符やパッセージのパターンや特徴が分かったら、それがうまくいくやりかたを探す手間を惜しんではいけません。
ゆっくりテンポでの練習から、指定テンポで演奏した際にそのやり方が通用するのか観察します。
特に、体の使い方においてはスムーズに次の運指に移れるか否かを判断します。
また、メンタルについても、本番でどのような状態でありたいかを、この時点から練習に盛り込みます。
すなわち、「できた・できない」ではなく、「こうやるんだ」という決意を持って臨むのです。
パッセージの最小単位のグループからはじめ、次第にそれをつないでいき全体のやりかた、すなわち体と心の使い方を探していきます
必要に応じて、アレクサンダーテクニークや4スタンス理論などのレッスンを受けると良いでしょう。
やりかたを自分に教える
「このやりかただ!」を見つけたら、それを自分に教えていきます。
このステップも飛ばしている方が多いです。
自分に教えることをしないで、ただ「できた/できなかった」のジャッジだけで練習するので、本番や合奏で混乱するのです。
私たちは、脳が知っていることのみスラスラと実行できます。
自転車の乗り方も知らないのに、いきなりは乗れませんよね。
前のステップで見つけた演奏のしかたを、自分に丁寧に優しく教えましょう。この期間を十分に取ることが、質の高い演奏に繋がります。
まるで、自分が自分自身に親身に教える先生になったように行いましょう。
-
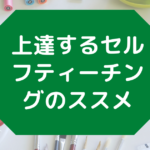
-
セルフティーチングでクラリネット上達のススメ
はじめは順調だった上達が止まったずっと練習しているのに上達を ...
続きを見る
指定テンポ60%でスラスラ度をあげていく
まだテンポアップには入りません。
次のポイントは「スラスラ度を上げること」です。
3で自分自身に教えたやり方を、スムーズに演奏としてアウトプット(思い出して実行)する練習をするのです。
この演奏としてのアウトプット練習をおこたると、本番で苦手パッセージを演奏するときに体が固まったり頭がフリーズします。
これはすなわち「何をすべきなのか思い出せない状態」です。せっかく練習したのに、本番で思い出せないのでは意味がありません。
「思い出す練習」が必要なのです。
このフェーズでは、本番テンポの60%を目安に、該当のパッセージを暗譜で演奏します。例えば本番テンポがbpm=138であれば、 bpm=80、84程度です。
本番テンポ60%で恐れやあやふやさがある場合は、50%から実施し、60%までスラスラ度を上げます。暗譜で演奏し、なんの不安も詰まりもなく演奏可能になったらいよいよテンポアップに入ります。
テンポアップ期間
テンポアップはこのタイミングです。
やり方を知り、自分に教えて、スムーズに思い出すことができるからこそ、テンポアップが可能なのです。
テンポアップには様々な手法がありますが、社会人で毎日楽器が吹けない方にオススメの方法はこちらです。
Step1:楽器を吹けない日のテンポアップ練習(下ごしらえ練習)
- パッセージの音名をリズム通りに声に出す。
- 音程は不要。bpmは本番の60%~70%程度でOK。
- 一箇所あたり3回。
- エア楽器練習。
- 音名をリズム通りにに声に出しながらエア楽器で運指もつける。
- bpmは本番の50%。
- 本番で自分と自分のメンタルがどのようにありたいか強烈にイメージする。
- 一箇所あたり3回。
以上の練習を行った上で、楽器演奏可能な日は次のようにテンポアップを進めます。
Step2:楽器演奏可能日の練習
- まずは思い出す。
- パッセージを見てリズム+音名歌い。
- 暗譜で演奏。これも思い出す作業。
- 前回練習で到達したテンポの1段階ゆっくりから開始
- そこから3段階上まで順に上げる。
- 各テンポ2回まで演奏
- 3段階下げながら練習。
- 各テンポ2回まで
- どうしても不安やパニックが起こるテンポに当たった時は、その1段階遅いテンポでその日の練習をやめる
- 次回練習は今回スタート時より1段階だけ速いテンポからスタート
Step2について具体例を示します。
例
例えば前回練習でbpm=96まで到達した場合、
1、♩=92→96→98→100 とあげていく
2、♩=98→96→92 と戻ってくる
各テンポ(上り下り共に)演奏は2回まで。
ターゲットは小さく絞る。
次の練習(翌日以降)は♩=96 からスタート。
これは打楽器奏者の福島あつさんがTwitterで紹介されていた方法です。
私も取り入れていますが、とても効果的です。
テンポ80%で演奏の質を上げる
見事に本番テンポを達成した後は、その80%程度の速さで演奏の質をあげていきます。
よくあるパターンは、速さ100%で練習を続けることですがこれには落とし穴があります。
それは、そのテンポでしか吹けなくなることと、細部の精度が疎かになることです。
本番では何があるかわかりません。指揮者が突然遅く振ることもあるし、ピアニストがいつもより速く弾くこともあります。
80%テンポで質を上げる期間を設けると、それらのトラブルにステージ上で対応できる質の高い技術を身につけることができます。
時々100%テンポで音楽のノリを思いすといいでしょう。
テンポの壁に当たった時
ある一定の速度より速くできない、いわゆる「テンポの壁」に当たるときがあります。私の場合はbpm=104前後がその壁です。
テンポの壁に当たった時、それを見て見ぬふりをして「ノルマだから」とメトロノームを速くしがちです。
しかし、自分の心や技術を誤魔化してテンポを上げることは、望まない癖や技術を練習してしまうことになります。そのままでは、不安や自分に対する疑問を持ったままステージに上がることになるので、のびのびと演奏できません。
ではどのようにテンポの壁と向き合うといいのでしょうか?
以下の方法をおススメします。
テンポの壁に当たったときの練習方法
①「テンポの壁」の70%程度まで速度を落とす
②演奏技術等に不安がないか、もっと楽になるところはないか、リズム等の誤解や不一致がないかよく観察しながら練習する
③メンタルもよく観察する。不安や焦りを見つけた場合は、なぜ不安なのか心を見つめる。事実を確認してやるべきことを明確化する
④「テンポの壁」の70%で安心してスラスラ演奏できるまで、次のテンポには進まない
⑤該当箇所の練習は長くても10分以内で切り上げる。
特に③を疎かにすると、恐怖や不安が演奏箇所と結びつき、本番でメンタルがくずれます。正直に向き合い、不安や焦りを口に出してみて、それが事実かどうか分析しましょう。
技術的な不安が頭をよぎった場合は、徹底して②を行いましょう。
速いパッセージも音楽に徹底しよう

作曲家は、音楽表現のために速いパッセージや連符を書いています。
あなたをいたずらに苦しめるためにあるのではありません。
そして、聴衆はあなたがどのくらい速く吹けるかを聴きにきているのではありません。
あなたがその音楽をその音楽たらしめている演奏を聴きたいのです。
速いパッセージも音楽に徹底しましょう。
まとめ
いかがでしたか?
人間の心身の機能を使い、それをトレーニングしていけば速いパッセージは絶対に演奏可能です。そういう風にできています。
闇雲にメトロノームに合わせるのではなく、手順を踏みながらじっくり自分に向き合い、適切な難易度を経験しながら取り組んでいけば、絶対大丈夫です。
ぜひ実践してください。

