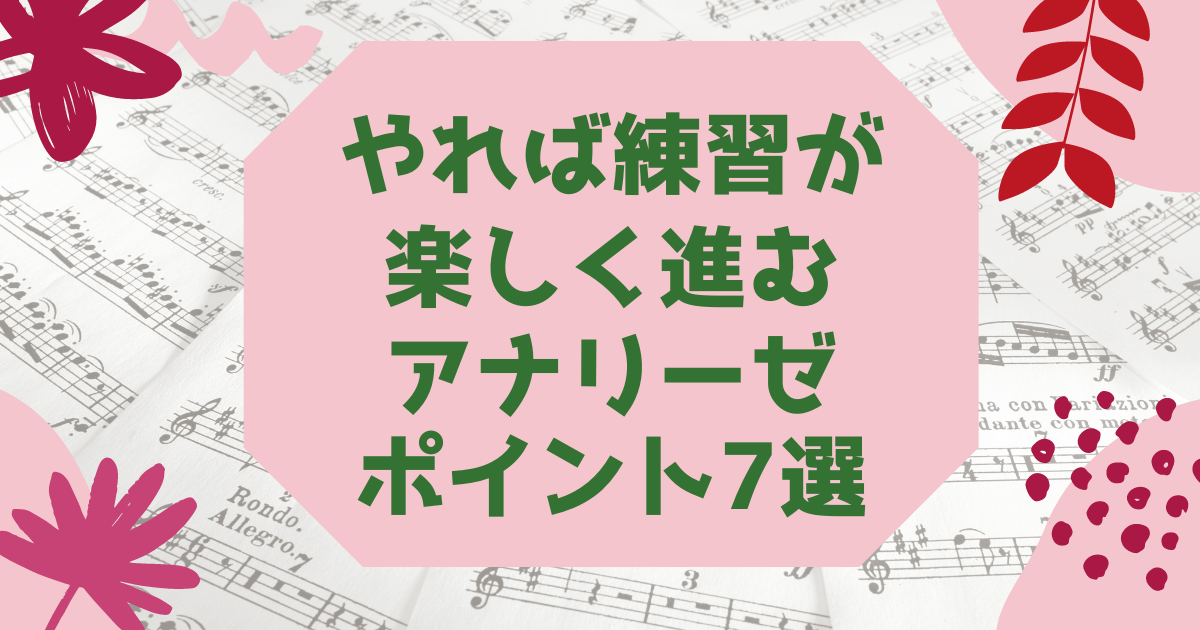作品を分析するアナリーゼ。
- 難しそう
- 面倒臭そう
- 時間がかかりそう
と感じますか?
でも、実はアナリーゼをすることで練習がぐんぐん進むんですよ!
この記事では、お仕事、家事、育児等で忙しい中でも楽しくできるアナリーゼのポイントを解説します。
アナリーゼ(楽曲分析)とは

音楽作品の要素や構造を調べることです。
音符を読んで運指をあてがうだけが譜読みではありません。
例えば、お友達が美味しい手作りクッキーを焼いてくれたとします。自分でも作ってみたいと思ったら材料や料理手順を知る必要がありますよね。
アナリーゼはこれに似ています。
観察ポイント
- どんな要素が使われているか(=材料)
- どんな形をしているか(=分量や型)
- どこが盛り上がりポイントか(=デコレーション、映えポイント)
- 結局何が言いたいのか(=味)
を、いろんな角度から観察します。
これらを知ることで作曲家の意図を理解できます。
すると、ただ音符通りに運指をあてがうよりもとても練習しやすくなり、演奏もより楽しくなります。
アナリーゼで楽しく練習が進む理由

アナリーゼをすると練習がぐんと楽しくなります。
その理由は以下の通り
- 作曲家からのメッセージがわかる
- どう演奏すればいいのかわかる
- 知識が増えて譜読みが楽になる
吹奏楽などでも「ここは歌って!」と指揮者から指導される場合がありますね。でもどうしたらいいか分からなくて困ったことはありませんか?
そんな時、アナリーゼをしてみると楽譜にはもう「答え」が書いてあることが多いのです。あとは、自分の音楽的創造を加え、それを実現するために練習すればいいだけ。
こうして、どんどん練習が進んでいくのです。そうすれば上達が自然と促進されます。
また、友達とアナリーゼした内容を話し合ったりすることで、アイディアが共有され、アンサンブルや吹奏楽などの団体演奏でも、練習がどんどん進みます。
つまり、アナリーゼをすることでお得に練習ができるのです。
では、どのようにアナリーゼを行えばいいのでしょうか?
何を調べて分析すればいいのでしょうか?
アナリーゼで抑えるべきポイント7選

「そうはいっても専門知識なんかないし、何をどこまでやったらいいのやら。。。」
まずはこの7つのポイントを調べるだけでも練習が楽になりますよ!
- 作曲家について
- 拍子
- 調性
- 音楽用語
- 形式
- 様式、曲のタイプ
- 作曲の背景
では、ひとつずつ見ていきましょう。
① 作曲家について
生没年月日(時代)、国籍、特徴、他の作品について調べてみましょう。
特にクラシック音楽は時代の変化や流行に大きな影響を受けたり与えたりしています。
また、物理的にバッハがドヴォルザークを参考にするなどということはあり得ません。
スタイルや音楽ルールがチグハグにならないよう、作曲家の生没年月日は必ず調べましょう。
② 拍子
拍子は音楽のノリを決めます。何拍子か認知しましょう。
③ 調性
何調か知ることで基礎練習を生かすことができます。
移調楽器の方は実音と記譜音名とでメモをとっておきましょう
④ 音楽用語
イタリア語、ドイツ語、イタリア語で書かれてあることが多いです。
音楽用語辞典で調べるだけでなく、Google翻訳などで、用語になる前の本来の意味を調べるのもいいですよ!
特に吹奏楽やっている方にオススメなのはこちらの本です。
ひと目で納得!音楽用語事典(関 孝弘/ラーゴ・マリアンジェラ 共著)
⑤ 形式
建物でいえばどんな形なのかにあたるのが形式です。専門用語としては
- 二部形式
- 三部形式
- ソナタ形式
- ロンド形式
- 変奏曲形式
などがあります。
が、用語やはっきりした形式が分からなくても次のように考えてみるといいでしょう。
- 練習番号AとFが似ている
- テンポの変化がある
- 急ー緩ー急だなぁ
- 似たメロディーが後半にも出てきた
などです。
形式がわかると、どのように演奏を進めていけばいいか見え、全体を捉えることができるので、演奏途中に迷子になることがなくなります。
ペース配分もできるようになります。
⑦ 様式、曲のタイプ
ざっくり曲のジャンルです。
- 序曲風
- 舞曲風
- マーチ風
- コラール風
曲が長いといくつかの要素が組み合わさっていることもあります。
作曲の背景
- 誰のために書いたか
- モデルになっている場所・出来事など
- モチーフ(動機)は何を表現しているか
- 暗号的な音の使い方
などの情報です。
吹奏楽などの新しい作品であれば、フルスコアに解説がありますのでメンバーでシェアしましょう。
遺跡や特定の場所がモデルになっているなら、Google Earthで見てみるのも楽しいでしょう。
楽しくアナリーゼするコツ

そうは言っても「面倒くさい」、「難しそうと」感じる方に、楽しくできるコツをご紹介します。
完璧を目指さない
これに尽きます。
学者になるわけではないので、完璧に調べ上げる必要はありません。
グループでわいわい取り組む
特にアンサンブルチームで一緒に調べるのがオススメです。
情報を共有できるので、練習もよりスムーズになります。
吹奏楽曲など大人数の場合は、パート毎やランダムグループに分かれて実施すると楽しいでしょう。
やりやすいところからやる
調べやすい項目から手をつけましょう。
インターネットで手軽に調べられるよい時代です。
不明点はすぐ質問
20分程度調べても分からない場合はすぐ質問しましょう。時間がもったいないです!レッスンの先生、専門家、ピアノを弾く友人なら調性や和声が詳しいでしょう。
また、吹奏楽部でしたら、教科担当の先生に質問するのも楽しいです。
英語教諭にタイトルの意味や発音を質問したり、音楽の先生にリズム、音楽用語、調性について。世界史の先生に、作曲された時代について質問するのも楽しいでしょう。調べたことを夏休みの自由研究としてまとめるのもいいですね。
そして専門家にも頼りましょう。インターネットでアナリーゼを手伝ってくれる人を探すことができるのも現代は可能です。
まとめ
いかがでしたか?
- アナリーゼとは作品の中身をしって理解を深めること
- アナリーゼで演奏の仕方や音楽の方向がわかって練習が楽しく進む
- まずは7つのポイントを調べてみよう
- 作曲家について
- 拍子
- 調性
- 音楽用語
- 様式、曲のタイプ
- 作曲の背景
- 工夫するとさらに楽しくアナリーゼできる
- 完璧を目指さない
- グループでわいわい楽しく
- やりやすい項目から
- わからなければすぐ質問
ということを解説しました。
仕事等で時間が限られると、すぐに音出しから練習をしてしまいがちです。
ですが、簡単でいいのでアナリーゼをすると、貴重な練習時間での能率がグンと上がります!
ぜひ取り組んでみてください。