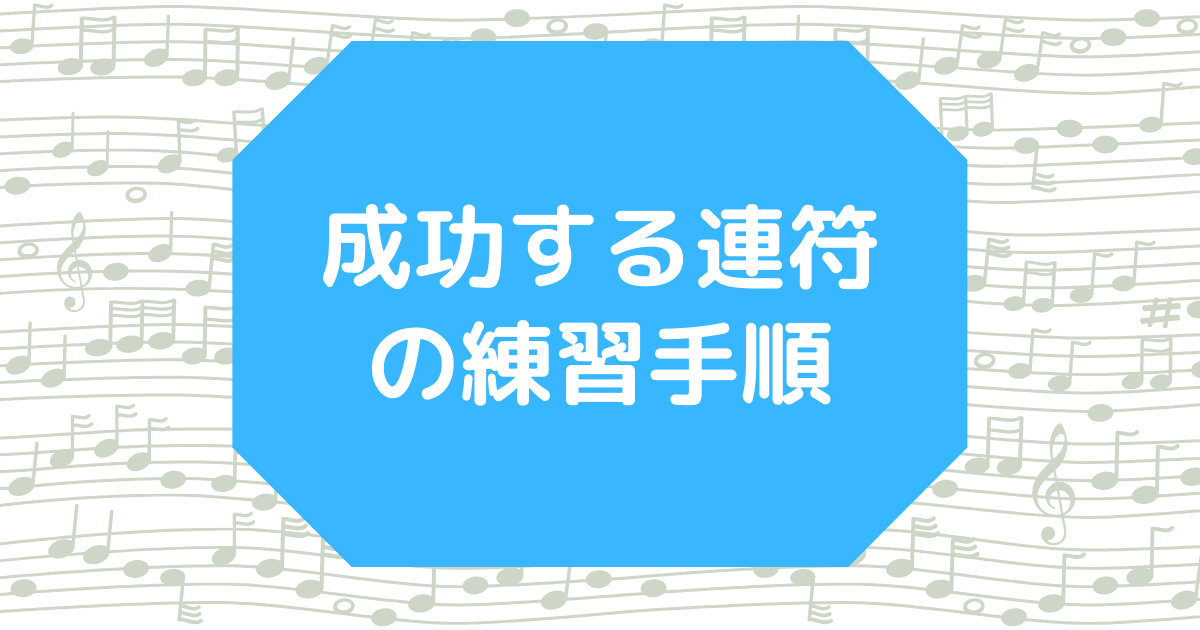「連符は得意ですか?」
そう問いかけられてYESと答える方は珍しいです。
残念ながら、吹奏楽部等で連符の練習方法やメンタルの使い方を詳しく教えてもらえる機会は殆どありません。
そのため、多くの方が誤った方法で練習し技術的に伸び悩みます。
更には全員の前でできるかどうかチェックされたり、理不尽に叱られたりしてトラウマを抱える方も多いです。
こうして連符への苦手意識や恐怖が心にこびりつきます。
でも大丈夫!手順を追って練習すれば連符は怖くもなんともありません。必ず美しく演奏できます。
この記事では、成功する連符の練習手順を解説します。
連符の役割は何?

クラリネットによく出てくる連符。そもそもなんのためにあるのでしょうか?考えたことありますか?
- 曲を華やかに
- 和音の中身を見せて変化を見せる
- コントラストをつける
- 躍動感を出す
- 音楽の方向性を出す
- 動物、自然現象、心情の動きを表現
などなど、音楽的な役割が必ずあります。
決して奏者を困らせるため、いたずらに難易度を上げるためではありません。
楽譜に連符を見つけたら、見ないフリをするのではなく、音楽的な役割を想像したり探ったりしましょう。
これが連符演奏成功に欠かせない第一歩です。
連符は速い?
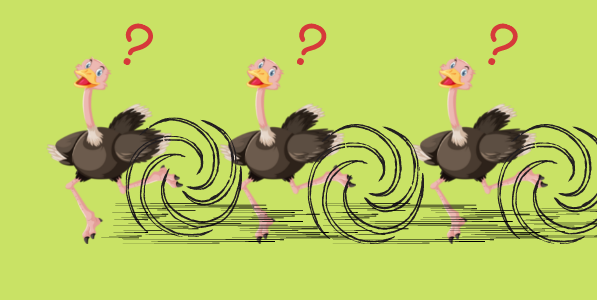
16分音符の連続を見るだけで「速く吹かなくちゃ!」と体が硬くなったり、心が焦ったりしていませんか?
そもそも連符とは速く吹くことが目的なのでしょうか?
例えばBPM=126の指示がある曲があるとします。テンポは音楽表現の一部です。こういう時間の流れで作品を表現して欲しいのです。
さて、そこに十六分音符で構成された4小節間のパッセージがあるとしましょう。これを「連符」と呼ぶことにします。
この連符の部分だけ、テンポが速まったりはしません。あくまでBPM=126の世界があり、四分音符ひとつの中身を4つの音で構成しているだけです。これが淀みなく演奏されることで、その音楽の言いたいことが表現できます。
そして、聴衆は「速い演奏」を聴きにきているのではありません。
その音楽がもつ自然な「スラスラさ」が実現できていれば聴いている方も心地がいいです。
連符は速く吹くものではなく、スラスラ吹くものなのです。しかも時間をたっぷり使って演奏するものです。
また、この十六分音符の連続はリズムです。リズムを無視して速く吹いても音楽的には何も実現しません。
失敗する連符練習方法の例

私の苦い経験も含めて、失敗するやりかたの例をあげます。
失敗する連符練習の例
- 個人練習しない
- 何調か理解してない
- 頭の中に音が鳴っていない
- 全ての音を単独で考えている
- いちいち目で判断しながら吹く
- 意味もわからずリズム崩し練習
- 余拍を取らずにひたすら繰り返す
- 1回の練習でインテンポを目指す
- 連符練習だけ違う姿勢でやっている
- 何十分も同じ場所を練習し続ける
- 音楽的な意味をわかろうとしない
- 演奏方法がわかってないのに反復する
- 耳を使わず指運動だけでなんとかしようとする
- ひっかかりポイントを無視してとにかく全体を通す
- 不安でドキドキしているのに速いテンポで無理にやる
- 日々メトロノームを上げていけばなんとかなると思っている
心当たりありますか?
こういった練習習慣の積み重ねで演奏しづらい癖がついていきます。それは身体的にもメンタル的にもです。
そして連符が嫌い、連符が苦手になるのです。
しかし、クラリネットという楽器は連符が得意な楽器です。そういう風に設計されています。連符もクラリネットの役割であり、演奏していてとても楽しくやりがいがあります。
では、どのような手順で練習すれば、連符を心から楽しんで美しく演奏できるのでしょうか?
-
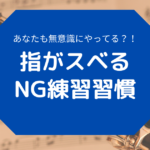
-
クラリネットで指がスベるNG練習習慣はコレ
余拍をとって練習していないから指がスベる 指がスベるどうして ...
続きを見る
成功する連符の練習手順と方法

スラスラ連符を吹くための練習手順は以下の通りです。
連符の練習手順
- 音楽的判断
- パターン分析とグルーピング
- 練習ターゲットを見つける
- 自分に教える
- テンポアップ
- 質を高める
ひとつづつ解説します。
1:音楽的判断
その連符が表現したいことはなんでしょうか?
例えばマーチなどでフレーズの最後を連符で終えているものがあります。
こんな感じ

最後の連符は、伸ばし音でもよかったはず。それにも関わらず上記のように書いた理由を想像します。
- 華やかに終わりたい
- 前向きな気持ちを表現したい
- 鳥が飛び立つ様子を表した
- 風がヒュンと吹く場面
タイトルや作曲の背景などを参考に想像の翼を広げましょう。
パートやセクションの仲間と話してみるとより楽しいです。
2:パターン分析とグルーピング
連符はただランダムに音が並んでいるわけではありません。必ずパターンがあります。
パターンを把握すると、これまでの経験や今ある技術を使いながら吹けるようになります。
パターン分析とグルーピング
- 調の判断
- 音の並びパターンの判断
- ダイアトニックスケール
- 分散和音
- おしゃれ盛り系
- それ以外
- グルーピング
- 記憶しやすいグルーピング
- 音楽的なグルーピング
「おはよう」が「お」と、「は」と、「よ」と、「う」ではなく「おはよう」と一言としてグルーピングされて私たちが覚えているのと同じ仕組みを使うのです。
このように順序だてると、スケール練習にもなり新たなテクニックの習得にもつながります。
たとえ初めて出会うパターンでも、分析して行えば自分の実力アップになり、次回以降の役に立ちます。
3:練習ターゲットを見つける
十六分音符の連なりの全てが吹けてないわけではありません。
そのうちのどこか1箇所、2つの音のつながりに何かしら不都合があって連符のスムーズさが阻害されていることが多いです。
その2つの音のつながりこそが練習ターゲットです。
それを無視して、全体を何度も通して練習しても時間と体力の無駄です。
上達しないどころか、うまくいかないやり方がデフォルトになり、引っかかることで常にイライラや落ち込みを感じ、練習に最も大切な「前向きな姿勢」を見失います。
ターゲットの早期発見が練習の能率を上げ、舞台で使える技術とメンタルを育てます。
よく聴いて、よく観察して、練習ターゲットに忍耐強く取り組むことが成功の鍵です。
4:自分に教える
ここも大きな落とし穴なのですが、やり方を知らないうちに反復練習しても意味ありません。
その連符の吹き方をまずは自分に教えましょう。
体の動かし方、タイミング、メンタル、全て本番の舞台で使えるやり方をゆっくりテンポで自分に教えます
知らないことはスラスラには吹けません。英語を知らない人は、英語を話せないのと一緒です。
特に、クラリネットは自分の手元をみてトーンホールやキーの位置を確認しながら演奏することは不可能です。とても繊細な動作を持ってノー・ルックであれほどの譜面を吹き切っているのです。
なので、自分に教える時間を十分にとり「その連符について詳しい状態」を作ればいいのです。
知っていれば怖いことはありません。
5:テンポアップ
テンポアップのタイミングはここです。
その連符がどんなものか知り、やり方を知ってからテンポアップします。
1~5のステップを飛ばしてテンポアップしようとするから、恐怖と焦りばかりを育ててしまうのです。
そしてテンポアップは、今のテンポが怖くもなんともなくなってから次のテンポに進みます。
「ノルマだから」とテンポを上げていっても、恐怖と不安がセットで記憶され、本番で混乱し、失敗するのです。
テンポアップが途中でつまづく場合は、大抵は上げるのが早すぎるのです。
ちなみに、質の良いスケール練習を長年行っていたり、和声や調に関する知識とソルフェージュ力を十分に持っている場合、1~4のステップを短期間で済ますことができます。(初見力がある方の特徴です)
6:質を高める
連符は速く吹ければいいわけではありません。
和声の流れ、拍感(拍子感)、音楽のベクトルがわからないと、いわゆる「棒吹き」です。
(この棒吹きが「上手い」の基準になっているところが少なからずある現状を危惧しています)
加えて、本番で指揮者やピアニストが本番と同じテンポで演奏するとは限りません。
さらに、人間は緊張による鼓動の速さから、本番ではいつもよりテンポが遅いと感じ、速く吹こうとする場合がとても多いです(本番でなぜか走ってしまうメカニズムがこれ)
なので、連符演奏の質を高めることも、実力を発揮する大切な要素になります。
連符の質の高め方
具体的には
- 一旦インテンポを達成したら、その80%のテンポで演奏する期間を取る
- 適度に練習を休んで記憶を醸成する
こうすれば、いかなる状態でも本番で連符を美しく吹き切ることができます。
-
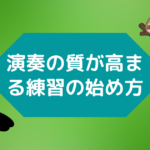
-
クラリネットの演奏の質が高まる練習の始め方
「さぁ!今日も部活の時間だ!」「よっし!今日は楽団の練習日だ ...
続きを見る
まとめ
いかがでしたか?
連符は決して特別な技術ではありません。クラリネットにとっては自然な演奏時間であり、コツコツ練習すればかならず成功します。
一般吹奏楽団や市民オーケストラの練習と演奏会がもっと楽しく充実したものになるでしょう。